兵庫県姫路市の離婚法律相談所 | 離婚問題・離婚相談は、弁護士がお答えする城陽法律事務所へ
ご予約・お問い合わせはこちら
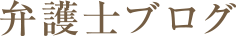
不貞行為の対象について
「不貞行為」の端的な例が、性交渉であることは、
知られております。
それでは、不貞行為にどのレベルのものが入るのでしょうか。
この点、最高裁は、「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」
が侵害された場合に、不法行為に基づく慰謝料請求が認められるとしています。
このため、例えば、配偶者に内緒で、風俗店で勤務していたという場合でも、
一般的な不貞行為のイメージとは異なるかもしれませんが、「婚姻共同生活の平和の維持」
が図 ...
財産分与でよくある誤解
今回は、財産分与の基準時が「経済的分離がなされた時点」である事について
お話しします。この点につき、一般的に誤解が多いため、要注意です。
離婚を成立させる際に、財産分与についても取り決めを行う事が
一般的です。
財産分与については、いつの時点の財産を基準に、価値を分け合うかが問題となります。
この点は、「別居開始時の数量を基準とし、価値が変動するものについては、財産分与の取り決めを
行う時点、すなわち、調停であれば調停成立時点、訴訟であれば口頭弁論終 ...
離婚原因、離婚意思の認定について
離婚をする際、双方が離婚に合意すれば、協議離婚や離婚調停は成立します。
これに対し、一方が離婚する意思をもち、他方が離婚する意思がない場合、
法律上の離婚原因が必要となってきます。
離婚原因の典型は、DVや不倫です。
特に、身体的な暴力や不倫が原因となり、離婚せざるを得なくなった場合には、
離婚が認められやすいと言えます。
ただし、離婚が認められやすいと言っても、暴力や不倫などにつき、相手方が争わないか、
相手方が争った場合 ...
子の引渡の間接強制、養育費不払の場合の口座の特定等に関する法制審議会答申
調停や裁判で離婚問題を解決することが昨今増えてきている上、離婚に関する
情報が得られやすくなったことから、
離婚を成立させる際に、養育費の取り決めをされる事は、従前よりも多くの方が行われているものと
思われます。
他方で、養育費は離婚当初は支払いがなされるものの、後々、払わなくなってくる、という事が問題と
されております。
この点、現在の制度では、養育費の未払がある場合、相手方の給料を1か月分だけでなく、
滞納が解消されるまでは、将来の給 ...
財産分与と損害保険金
交通事故などの損害保険金は、様々な費目で構成されています。
具体的には、入通院期間に対応した傷害慰謝料、後遺障害が残った事に対する後遺障害慰謝料、
後遺障害が残ったことにより、収入が得られなくなった、あるいは特別の努力により収入が維持されている
場合等の後遺障害による逸失利益などです。
この点、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料については、事故により負傷し、入通院治療を受け、
後遺障害が残ったことにより、被った精神的苦痛を慰謝するためのものであり、配偶者の寄与が
存在しな ...
審判時の注意点
婚姻費用、養育費などについては、調停が不成立となった場合、
裁判官が結論を決める、「審判」という手続に自動的に移行します。
審判は、調停のように当事者の合意によるものではなく、
裁判官が当事者の提出した主張、証拠に基づき判断するものです。
このため、調停段階で、主張を口頭で述べるにとどめ、書面で提出していない
場合や、主張書面は出しているものの、裏付け資料(例えば、お子様に授業料がかかるとした場合の、
授業料の金額の分かるパンフレットや、自動振替のな ...
親権を一度取り決めた後の親権者の変更について
時々、離婚を早く成立させたいとのお考えから、親権を相手方として離婚を成立させ、
その後、親権者の変更を相談されるケースがあります。
親権者の変更については、親権者が頻繁に交代すると混乱を招くことから
(お子さんにとっても環境が変わることとなります。)、ハードルを高く設定して運用されているという
実感があります。
親権者を最初に決める段階では、これまでどちらが主に子の監護を行ってきたのか
(事実上の監護者が誰か)や、お子さんが幼少の場合の母性優先の原則 ...
「退職金」がない場合の財産分与の注意点
退職金も、離婚する際の財産分与の対象となることは、
比較的、多くの方がご存知なのではないかと思われます。
しかし、退職金の支給制度については、企業規模や業種等により、
存在しない会社も多いのが実態です。
退職金を退職時にまとめて支払う、従来の形の制度をとると、
会社の負担が大きくなってしまうこ事もその理由の1つかと思われます。
このような理由から、退職金の支給がない場合でも、「企業年金」制度を設けている
事があります。 ...
調停時の注意点
調停は、裁判所を利用した話し合いの1つであり、離婚事件の場合、
訴訟をいきなり起こす事はできず、まず調停を経る必要があります。
調停では調停委員2名が当事者双方の主張をきき、合意点を探ります。
調停委員の背後には裁判官がいるため、ある程度は法律に則った解決が期待できます。
しかし、調停とはいえ、裁判所を利用した手続ですので、裁判所がどちらか一方に肩入れする事が
できません。
また、訴訟ではないため、法的な通りやすさや立証の程度などをあま ...
よくある誤解-養育費の減額
養育費を取り決めるにあたり、義務者が再婚し、新たに子が出来た場合、
権利者の養育費に影響する、という解説がなされることがあります。
これは、元々の子と離婚後に新たに再婚相手との間で子が出来た場合に、
子2人の間に扶養義務の優劣がない、という事によります。
では、義務者が再婚したのみの場合には、養育費の額に影響しないのでしょうか。
この点は、大阪家庭裁判所作成のQ&Aによると、義務者が再婚した場合、新たな配偶者に対する
扶養義務が発生する事を前提に、権 ...