兵庫県姫路市の離婚法律相談所 | 離婚問題・離婚相談は、弁護士がお答えする城陽法律事務所へ
ご予約・お問い合わせはこちら
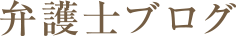
離婚調停に提出すべき証拠-㉘婚姻費用・相手方による預金等の引き出し
離婚調停に提出すべき証拠を今回も解説いたします。
ここでは、離婚調停に合わせて、婚姻費用分担調停を申し立てた際に、
別居に際して相手方が預金等を引き出した場合について解説いたします。
別居以降に相手方が、当方の預金から引き出しを行った場合等は、当方の預金から
相手方の携帯利用料などが引き落とされた場合と同様、婚姻費用の既払金に充当する事には
通常、争いはありません。
対して、別居に際して、あるいは別居以前に相手方が当方の預金から引き出しを行った場合な ...
統計から考える、離婚調停の動向
令和2年度までの離婚調停や婚姻費用分担調停などの家事調停の統計が示されています。
これを見ると、離婚調停などの婚姻中の夫婦間の事件については、
全国で平成30年4万4055件、令和元年4万3492件、令和2年4万1037件と
若干、減少傾向にありますが、新型コロナウイルス感染拡大等の影響もあるかと思われますので、
今後も続くのかは分からないところです。
また、令和2年度について、離婚調停などの婚姻中の夫婦間の事件については、46.1%が調停成立、
2 ...
運用の改正-離婚調停における電話会議・神戸家裁姫路支部の場合
離婚調停では、代理人として弁護士が選任されている場合でも、
原則、当事者本人の出頭が必要と考えられています(手続自体が進まない訳ではありませんが、
調停委員が直接、当事者に質問する事もあるため、来ていただく必要があると裁判所は考えています。)。
もっとも、遠隔地である等の場合に、裁判所への現実の出頭を要するとすると、交通費や労力がかかり過ぎるという問題が
あります。このため、離婚調停の手続代理人として弁護士が選任されている場合、弁護士の事務所と裁判所を電話会議で繋ぐことが
認 ...
法改正の動き-離婚調停、離婚訴訟におけるウェブ会議の利用
現在の法律では、離婚調停で、離婚を成立させるには、必ず当事者本人が
裁判所に出頭し、裁判官が本人確認をした上で、調停条項を読み上げた上で、双方当事者が
その内容で構わない旨、述べなければ、離婚調停が成立できない事となっています。
(この事は、本人が弁護士に手続代理人として委任している場合も同様であり、代理人弁護士が出頭するだけでは
足りません。)
これまでも、離婚調停を成立させる以外の途中の調停期日については、ウェブ会議の利用を認めたり、遠隔地で出頭が困難である場合や ...
法改正の動き-再婚禁止期間・離婚後の嫡出推定
法制審議会において、民法の親族法の中の再婚禁止期間の規定や離婚後の嫡出推定の規定について
改正する旨の要綱案がまとめられたとの報道がなされました。
これによりますと、まず、現行の民法では、「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を
経過した後でなければ、再婚することができない。」(民法733条1項)と定めているところ、
要綱案では、これを削除し、再婚禁止期間を置かない内容とするものとしています。
また、現行の民法では、「婚姻の成立の日から二百日を経過した ...
離婚調停に提出すべき証拠-㉗養育費・医療費
離婚調停に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、離婚に付随して養育費を請求する場合において、医療費による
特別の経費加算を求める場合について考えます。
婚姻費用や養育費の算定表においては、標準的な医療費については織り込み済みです。
(例えば、年収200万円未満の場合、4278円、300万円未満の場合、8859円)
これを超えるような医療費がかかっている場合に、婚姻費用や養育費の基本月額部分とは別に、
加算を求めることができる場合があります。
...
離婚調停に提出すべき証拠-㉖養育費・私立学校の費用
離婚調停に提出すべき証拠を解説いたします。
ここでは、離婚に付随して養育費を請求する際に、子に私立学校の費用がかかっている場合について
考えます。
まず、一定の収入以下の方については、高等学校等就学支援金が支給され、授業料が無償となります。
また、婚姻費用や養育費の算定表には、14歳以下の子については公立中学の標準学費年13万1302円が、
15歳以上の子については公立高校の年間標準額費年25万9342円が織り込み済みです。
従って、支援金を考慮しても自己負担せざ ...
離婚調停に提出すべき証拠-㉕養育費・塾の費用
離婚調停に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、離婚に際し、養育費を請求する場合に、子に塾の費用がかかっている場合について
考えます。
塾については、通う事が当然とまでは言えないため、負担を求めることが出来るかについては
ケースバイケースの判断となります。また、裁判官により、考え方も分かれるところです。
また、夫婦双方の収入の程度なども結論に影響することがあります。
例えば、発達障害などを抱えている場合に、補助的に塾や施設に通う場合の費用について ...
離婚調停に提出すべき証拠-㉔養育費・大学進学費用
離婚調停に提出すべき証拠をここでも解説いたします。
今回は、離婚調停において養育費の請求も行い、その際、大学進学費用の加算を求める場合について
考えます。
養育費において、大学進学費用の加算を求める場合、まずは、進学先が具体的に確定している事が
必要となります(従って、例えば、まだ高校1年生であり、大学進学予定というだけでは、現段階では、加算を求めることは出来ず、
進学時の費用加算は、後に別途協議とせざるを得ません。)。
具体的には、単に○○大学を志 ...
新年明けましておめでとうございます
皆さま、新年明けましておめでとうございます。
城陽法律事務所は本日6日9時~営業を開始いたしました。
離婚、親権、養育費など様々な問題にお悩みの方に、よりよい解決がはかれるよう、
本年も事務所一丸となって力を尽くして参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ...