兵庫県姫路市の離婚法律相談所 | 離婚問題・離婚相談は、弁護士がお答えする城陽法律事務所へ
ご予約・お問い合わせはこちら
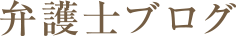
離婚調停に提出すべき証拠-73 親権、監護権に争いがあり、夫婦共に子の監護を行っている場合
離婚調停、訴訟等に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、親権者や監護権者(離婚成立以前の段階で、子の監護を行う者)をどちらと定めるか対立がある場合で、
夫婦共にこれまで子の監護を行ってきた場合について解説いたします。
未成年の子が存在する場合、離婚を行うには親権者を定める必要があり、親権者を定めることなく
離婚を成立させることは出来ません。このため、離婚調停をまとめるには、親権について合意に達する必要があります。
離婚訴訟の場合は、離婚が認められる場合には合わせて裁判官が親権を定める事となります。
この点、子の年齢が15歳以上の場合、親権や監護権を定めるには、裁判所は子の意見を聞かなければならない事と
なっております。これは、法律が15歳以上の子の場合、親権や監護権についてどちらの親に取得してもらうのが自分にとって
よいか判断する能力を有していると見ている事によります。
このため、子が15歳以上の場合、ほぼ子の意思で親権や監護権が決まる事が多いと整理する事ができます。
15歳に満たない場合でも、これに近い年齢の場合は、同様に尊重される事が多いと考えられます
対して、子の年齢が乳幼児、小学生低、中学年の場合、子の発達が未成熟であり、親権や監護権を決める上で
十分な判断能力を有しているとは言えない事から、夫婦双方に対する子の捉え方は親権や監護権を定める判断材料の1つという位置づけに
なる事が多いと考えられます。
子が幼少の場合は、同居中に夫婦のどちらが主に子の監護(身の回りの世話、幼稚園、学校、塾等との連絡、送り迎え、持参物の準備、宿題・勉強の付添等)
を行ってきたか、その内容に大きな問題がなかったか、という観点が親権、監護権を定める上での最も重要な要素と考えられております(その他、親権、監護権を
取得した場合に適切な監護がなされる環境、見通しが立っているか否かや、親権、監護権を取得した場合に、他方の配偶者に対して、子の面会交流についてどのような
スタンスを採る考えなのか等が判断要素となるとされています。)。
この点、夫婦のいずれかが専業主夫、専業主婦あるいはパート勤務という場合、必然的に子の監護の分量は
その方となる事が多く、その内容に大きな問題がない事を示す事で、その方が親権ないし監護権を取得すべきとの結論に
なりやすいと考えられます。
対して、夫婦が双方フルタイム勤務で、普段、子と接する時間に大きな差はない、というケースについては
どのように考えるべきでしょうか。
この点は、結局のところ、子の福祉の観点から、夫婦のどちらを親権者ないし監護者と指定するのがより適切と言えるかどうか、
という物差しで整理する事になり、その評価をどのように行うべきかについては、裁判官により異なり得るところであるため、
一般化する事は困難ですが、私は次のように考えております。
すなわち、子の監護は、食事は誰が用意しているのか、学校等の送り迎えは誰がしているのか、等細かく見ていく事となりますが、
誰が何をどの程度行っているのか(監護の量)のみならず、監護の内容、質についても考慮要素と考えるべきと考えております。
食事の用意さえすればよい、というのであれば、誰が用意しても(例えば、親自身が作らなくても、その親(子からすると祖父母)が作っても)
意味は同じという事になってしまいます。本来、食事には子の好き嫌いの克服や子の発育に応じた栄養バランスの確保、更には食育、
あるいは子とのコミュニケーションの機会等の大事な意味があるはずです。
また、子の勉強を見ている、と言っても、隣で携帯ゲームをしながら見ているのと、分からないところを適宜教えながら見ているのでは子にとって意味が異なります。
元々の判断基準は、子の福祉に適うか否か、という物差しであるため、子の性格、特性を考えて丁寧にきめ細かに対応されているのであれば、
その点も考慮されるべきと考えられます。
また、夫婦のいずれもがフルタイム勤務で、普段の子と接する時間にあまり差がないケースであっても、
実際には、子の事を決めているのはどちらか一方という事は多いです(例えば、子に○○の予防接種を受けさせるか否か、であるとか、
子が病気にかかった場合にどこの病院に連れて行くのか、とか、習い事として何をさせ、どこに通わせるか等)。
このように、子の重要事項について決定してきたのが主として夫婦のどちらか一方である、という場合には、重要事項の決定も親権、監護権の重要な
内容の1つである以上、例え日々の監護(食事の用意、送り迎え、風呂等)が同程度の関与であったとしても、重要事項の決定を行っている配偶者の方が
主たる監護者と整理する事が可能と考えられます。
証拠としては、陳述書の他、きめ細かく対応されてきた事を示すため、育児日記や育児で工夫されたことを示す写真(例えば、子と一緒に作った作品や
表彰状などの写真)、学校等の連絡帳などを提出する事が考えられます。
なお、親権や監護権の対立が激しい事案、どちらが主に分量的に主として監護を行ったとは言い難い事案では、
裁判官や調査官が、どの事実に着目して事案を分析すべきなのか、陳述書等の証拠を提出するのみならず、主張書面で
丁寧に論じる必要がある(そうする事で、裁判官、調査官に当方の主張の正当性を訴える)必要が高いと言えますので、
弁護士に事件を依頼される必要性が高いと考えられます。
(親権、監護権に争いがある場合、調査官による調査がなされる事が多いですが、親権や監護権を考える上で重要な事実、証拠の提出を、基本的には当事者がまず
行うべき事に変わりはなく、また、調査官によって全ての事実を網羅的にヒアリングされる保証もないため、調査官任せ、裁判所任せに
してしまう事は、いずれを親権者、監護者と判断されるか微妙なケースにおいては特に危険と言えます。)
新日本法規刊、武藤裕一裁判官、野口英一郎共著「離婚事件における家庭裁判所の判断基準と弁護士の留意点」123頁、武藤裁判官記部分も、
「一見父母の監護が拮抗する事案においても、単純な育児「量」と比較するだけでなく、いわゆる保活や入園語の保育園との対応、子の衣類や
持ち物の準備、子の発熱時の預け先の確保、子の発育上の問題についての相談、習い事の選定など、調査・調整・判断を要する事項を担い、
育児の司令塔的な役割を果たしていたのはどちらの親であるかを見極めることによって、主たる監護者を認定することが可能であり、かつ、
そのような見地から認定された主たる監護者の監護実績等を重視すべきですから、上記のような社会状況の変化(注.夫婦の生活スタイルの多様化や共稼ぎ夫婦の
増加等)を踏まえても、乳幼児に係る監護者としての適格性の判断における主たる監護者の基準の重要性は揺るぎません。」
と述べられているところです。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決を目指します。