兵庫県姫路市の離婚法律相談所 | 離婚問題・離婚相談は、弁護士がお答えする城陽法律事務所へ
ご予約・お問い合わせはこちら
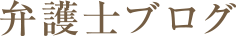
養育費に関する家族法改正-①先取特権-調停調書や審判書等がなくても差押え申立が可能になる場合ができました
家族法改正について解説いたします。
今回は、養育費に関する家族法改正のうち、「先取特権」について解説いたします。
養育費を相手方が任意に支払わない場合、現行法では、
・養育費の調停、審判ないし離婚訴訟の判決で養育費の支払条項の入った文書を取得する
・強制執行認諾文言つきの公正証書で、養育費の支払条項の入った文書を取得する
のいずれかを取る必要があります。このように、支払条項の入った裁判所の文書や強制執行認諾文言つきの公正証書などを
「債務名義」と言います。
現行法では、当事者間の合意書がある場合でも、養育費の支払を定めた債務名義をまず取得しなければ、相手方の収入や財産の差押えの申立てをする事が
できない、という問題がありました。(なお、この点は、養育費に限らず、貸金返還請求等でも同じことであり、当事者間の合意書や借用書は、債権の存在を示す方向で
働く1つの証拠に過ぎないという位置づけであり、まずは訴訟で判決を取得する等、債権の存在を公的に確定しなければ、差押えを申し立てる事ができない、というのが
原則であり、養育費も他の債権と同様に考えられていました。)
しかし、養育費は、月々が定額であり、合意していたのであれば、債務者は甘受すべきものと言えますし、月々、現実に支払を受ける必要性が高い
(あとで滞納した分をまとめて回収するのでは、生活に支障を来す可能性が高くなる)と言え、保護の必要性が高いと言えます。
そこで、家族法改正により、養育費について、「先取特権」の規定が新たに設けられました。
これにより、養育費の調停調書や審判書、強制執行認諾文言つきの公正証書等がなく、単なる当事者間の合意文書しか存在しない場合でも、
「先取特権」に基づき、養育費支払義務者の収入や財産の差押えの申立てが可能となります。
但し、注意すべき点が2点考えられます。
1点目は、債権の額が具体的に定まっている必要があるという点です。
債権の額が具体的に定まっていない場合、差押えの申立時点で、いつからいつの分のいくらを滞納しているのかが不明であるため、
差押えの決定が出来ないという事になります。
2点目は、養育費の「存在を証する文書」が民事執行法上、要求されるという点です。
この点、立法担当者の解説では、「公文書である必要はなく、弁護士等の法律専門家が作成いた文書である必要もない。」とされています
(「家庭の法と裁判 53号」110頁「父母の離婚後の子の養育に関する「民法等の一部を改正する法律」の解説(2・完)」)。
しかし、債権の存在を証するためには、最低限、誰が誰に対してもつ債権なのか(債権者及び債務者の特定)及び債務者の真意に基づく
債務の負担の意思が文書上、現れている事が必要であるように思われます。
なお、法改正により、養育費の合意書を当事者間で作成した場合でも、合意の有効、無効が後に争われる可能性も
考えられるため、強制執行認諾文言つきの公正証書で定める、あるいは離婚ないし養育費の調停調書、審判書、離婚訴訟の判決で
養育費を定めた文書を取得する事の有用性はなお残るように考えます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決を目指します。