兵庫県姫路市の離婚法律相談所 | 離婚問題・離婚相談は、弁護士がお答えする城陽法律事務所へ
ご予約・お問い合わせはこちら
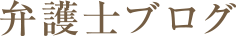
家族法改正による離婚調停、訴訟への影響①-親の責務の規定の新設
新聞報道等で、家族法が改正され、共同親権が選択可能となる事などご存知の方も
多いかと思われます。今回の改正は、令和8年5月までに施行される予定ですが、
施行後、離婚調停や離婚訴訟にどのような影響が考えられるのかについて解説いたします。
今回は、家族法改正により新設された、子への親の責務の規定について考えます。
親権については、改正法以前にも民法に規定が存在しました。
しかし、親権を取得しなかった親が子に対して負う責任については明示的な規定は存在しませんでした。
改正民法817条の1の第1項では、
「父母は子の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び
発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活が維持できるよう
扶養しなければならない。」
と定められました。
「父母」「自己と同程度の生活が維持できるよう扶養しなければならない。」とあるように、親権を有するか否かにかかわらず、
子の父母は、扶養義務、具体的には、自己と同程度の生活が維持出来るよう扶養する義務(生活保持義務とも言います。)を
負う事を明文で明らかにされました。
今回の改正により、共同親権の選択が可能となり、
①元々離婚時に単独親権の定めを行ったものの、
後日、共同親権あるいは自身のみを単独親権とする旨の変更の調停、審判を求める、
②改正法施行後に離婚を行い、共同親権の定めを行ったが、一方のみを単独親権とする旨の
変更の調停、審判を求めるというケースが考えられます。
これらのケースにおいて、例えば、養育費の定めを離婚時に行ったにもかかわらず、養育費の支払義務者が養育費を全く支払わない、
という事情は、改正民法817条の1の第1項に反する事となり、このような事情は、①や②の変更を認めるべきである、との方向に働く
判断材料の1つになり得るものと考えられます。
また、改正民法817条の1の第2項では、
「父母は、婚姻の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の離婚に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し、
協力しなければならない。」と定めています。
例えば、離婚時に共同親権の定めを行ったものの、子の監護に関する重大な事項(例えば、進学等)について、協議を行うべく
連絡を取っているにもかかわらず、何ら応答しない、などの事情がある場合には、①、②の手続において、
変更を認めるべきである、との方向に働く判断材料になり得るものと考えられます。
改正民法817条の1の第1項、第2項はともに、当たり前の事を規定していると言えますが、
明文化された事で、親権者としての適格性の判断に影響を与える重大な事由となり得る事項である事がよりクリアになったと言えます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決を図ります。